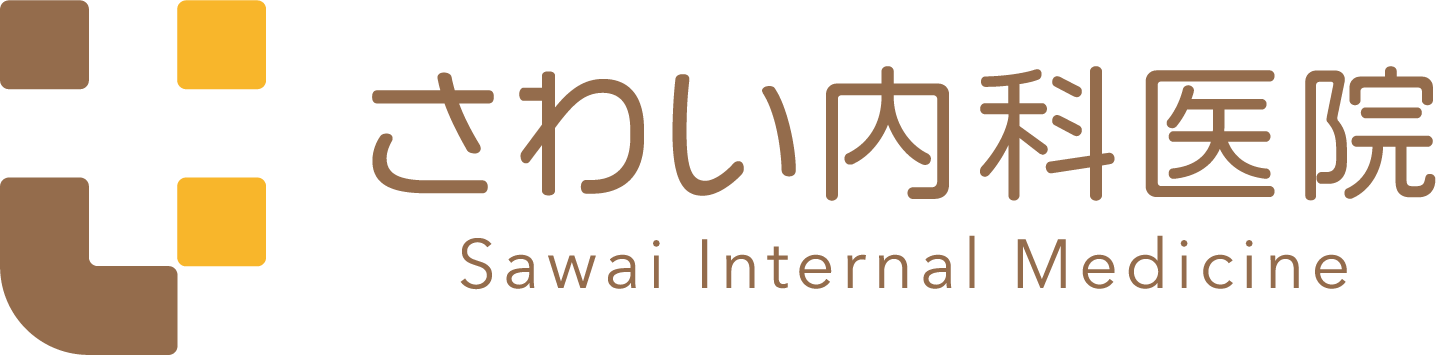お知らせNEWS
2024.06.24 熱中症とは 〜予防のために知ろう
「日本の夏」といえば、「スイカ」「花火」「甲子園」など風物詩に事欠きませんが、医療者にとっては「熱中症」の季節です。今年も暑くなり、メディアでも「熱中症」の名前が聞こえてくるようになりました。
京都府では昨年(2023年)5月から9月の間に2220人が熱中症で救急搬送され、うち4人の方が亡くなっています。

熱中症は命に関わる病態ですが、同時に予防可能なものです。熱中症の仕組みを知ることで予防対策の意味を理解し、適切な対応が取れるようになるのは大切なことだと思います。
ここでは体温調節の仕組みと、それに関する問題に応じた対策についてご紹介します。(1番下にまとめ)
体温調節 〜熱の産生と冷却のサイクル
ヒトの体温(深部体温)は体の働きに最適な環境を保つため約37℃に維持されており、体温調節には①外的環境、②血液量、③心機能、④筋肉運動(熱の産生)などの要素が影響しています。それぞれの要素の関連は「深部の筋肉で産生された熱(④)が、心臓のポンプ(③)で豊富な血液(②)にのって体表に運ばれ、体表で冷えた血液(①)がまた体の深部に戻る」とするとわかりやすいと思います。(下図)

上の図に示した、体温上昇(熱産生)と体温抑制のサイクルのどこかに問題が生じると体温が上昇し、熱中症(高体温)の引き金となるのです。
たとえば、
①外的環境:暑い、蒸し暑い、風がない、直射日光を浴びている → 体表で血液を冷やせない
②血液量:大量の汗をかいているのに水分補給ができない → 血液量が足りず熱を運び出せない
③心機能:狭心症、不整脈などの疾患がある → 心臓ポンプが弱く熱を運び出せない
④筋肉運動:休憩なしで運動を続ける → 筋肉での熱産生が過剰
このような問題が1つ以上あると体内に熱がたまりやすくなり、体温が上昇するのです。
制御できないのが問題 〜発熱と高体温
ちなみに、「発熱」と「熱中症(高体温)」の違いは、状況に応じて視床下部(脳)で調整される設定体温にあります。風邪の発熱には設定体温を上昇させてウイルスなどの病原体を撃退する意味があります(制御されている)。これに対して熱中症での高体温では、設定体温は平熱にもかかわらずうまく冷却されないために、体温上昇が制御できなくなってしまいます。体温調節が制御できていないということは、休んでいるだけでは対応が不十分なこともあり、そのために予防と対策が必要なのです。
熱中症予防 〜仕組みがわかれば理由もわかる
熱中症の仕組みとしては、①外的環境、②血液量、③心機能、④筋肉運動が重要であることがわかりました。このいずれかに問題が生じると熱中症の引き金を引くことになるのであれば、それぞれに対策を講じることができます。
①外的環境
①−1 暑さ指数(熱中症指数)の活用
熱中症の発生件数は6月から上昇して7、8月にピークを迎えます。これは夏に気温が上がることが最も大きな要因ですが、実際には湿度、日射、風邪の有無、輻射熱などが影響しています。「暑さ指数」は熱中症予防のため国際的に採用されている評価指標で、WBGT(wet-bulb globe temperature:湿球黒球温度)とも言います。(過去記事:暑さ指数について)
暑さ指数では気温以外の指標も考慮されており、指数の高さと熱中症発生率上昇は密接に関係していることがわかっています。環境省の熱中症予防情報サイトでは、日本各地の暑さ指数をリアルタイムで知ることができるので、外出時や普段と異なる活動を行う際にはご活用ください。

①−2 室温を28℃に 〜「28℃設定」ではない
冷房使用時は28℃以下を目安に室温を維持するようにしましょう。あくまでも目標温度が28℃であり、設定温度ではないことに注意してください。実際の室温を測定できるようにしてください。
室内の空気がこもっている場合は換気することも必要です。扇風機やサーキュレーターで室内の空気を循環させると効率よく冷房を使用できます。
環境変化が大きいと体の負担となるので、室温を下げすぎないことも重要です。
②血流量
水分摂取 〜水だけではいけない、スポーツドリンクも場合による
適切に冷房を使用し活動量も少ない場合は、通常の食事がとれていれば過剰に水を飲む必要はありません。こまめな摂取が大切です。外出時に暑さ指数を参考に水分摂取を心がけて下さい。
積極的な予防対策としては水分のみの補給は推奨できません。熱中症の発生が心配な環境では水分とともにナトリウム(塩分)などの電解質が失われており、これらの補給も必要です。経口補水液(ORS:OS-1など)は塩分と糖分が適切に配合されており熱中症予防の水分補給に有用です。
スポーツドリンクは糖分が多く含まれているので糖尿病の方は気をつけましょう。スポーツや肉体労働で大量の汗を長時間かく場合にはスポーツドリンクでの水分補給も可能ですが、基本的には経口補水液が望ましいです。

③心機能
リスクの自覚と、それぞれの対策
心筋梗塞や狭心症、不整脈がある方は注意が必要です。心機能が弱っていると血液の運搬能力が落ちて体温冷却の能力が低下していると考えられます。また、臓器が血流不全に陥ると熱中症は重症化しますが、心機能が低下しているとこの危険性も高くなります。これらの病気がある方は重症化リスクが高いことを自覚して、暑さ指数を参考に適切な冷房の仕様、暑熱環境を避けるなどの対策をしてください。予防策も基礎疾患に合わせて変える必要があるので、かかりつけ医に相談してください。
④筋肉運動
やめる、やめさせる状況を想定する
長時間のスポーツや肉体労働では熱中症のリスクが高まります。とくに小児の体育、部活やスポーツイベントは暑さ指数を参考にして、中止や延期も最初から想定の範囲に入れておくべきです。暑さ指数で可能であると判断できても、個人の状態によっては熱中症のリスクはあり、場合によって指導者、管理者は活動を中止させる判断が求められます。
労働においてはつなぎ服の使用やその素材、また冷房使用下でも作業強度や作業内容により熱中症のリスクが高まることが知られています。中高齢者には基礎疾患も多いので、日常的な体調管理が重要です。事業所では厚生労働省の指針に沿った対策を講じることが求められてます。(厚生労働省:STOP!熱中症 クールワークキャンペーン)

何度も言いますが、熱中症は命に関わる病態でありながら、十分に予防が可能です。
下に記事をまとめましたが、予防の基本は涼しく、通気の良いところにいることにつきます。
夏の風物詩を楽しむためにも、熱中症予防を心がけるようお願いいたします。
まとめ
・暑さ指数を参考に、室温は28℃以下 (冷房の「設定温度」ではない)
・通気の良い服装、環境を心がける (体温を下げられる環境づくり)
・水分補給は経口補水液(ORS)を使用する (スポーツドリンクも場合によってはダメ)
・心疾患がある方はリスクの自覚をする (予防対策もかかりつけ医に相談)
・スポーツや作業をやめる・やめさせる勇気 (指導者、管理者の責任は重い)