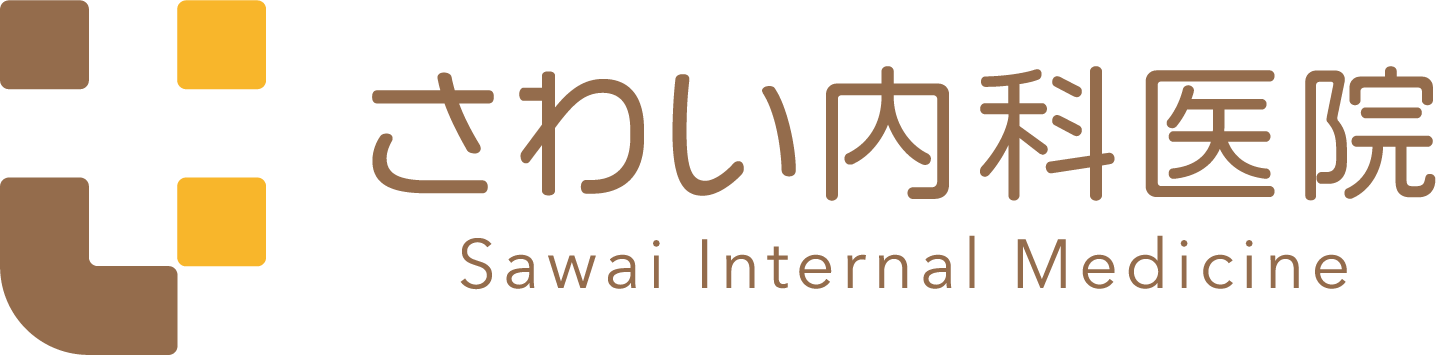お知らせNEWS
2024.06.10 痛風と尿酸 〜痛いだけではない
今年も夏が近づいてきました。気温の上昇とともに話題になるのが熱中症ですが、それに先立って「痛風」が春から夏にかけて増える傾向にあります(追記 R6.12.12:誤解を与える表現でした。冬にも増える傾向があります)。詳しいことはわかっていませんが、気温の変化に体が追いつかないことや隠れた軽度の脱水が引き金となるなどの説があります。
痛風 〜名は体を現す
「痛風」はみなさんご存知の病名かと思います。痛風の痛みは激しく、「風が吹いいただけでも痛い」ということから名づけられたとも言われています(諸説あり)。古くはエジプトのパピルスに記載があるそうで、人類は実に永くこの病気とつきあってきたということになります。つきあいが長いだけに、痛風の原因は「尿酸」であることは有名であり、さらには尿酸は「プリン体」がもとになって体内でできることまでご存知かもしれません。

痛風の痛みは、血中の尿酸値が高い状態が持続することで尿酸結晶が関節内にたまり、その結晶を異物として認識する白血球や炎症細胞の活性化によって急性関節炎が生じることによります。発作は激しい運動(無酸素運動)や飲酒・発汗(サウナ)による脱水状態などが引き金となりますが、とくに誘因なく痛みが襲ってくる場合もあります。

痛風は、体内でプリン体からできる尿酸が関節内で結晶をつくることが原因であり、血清尿酸値が7mg/dL台では10%、8mg/dL台では20〜40%、9mg/dL以上では50〜90%が数年以内に痛風発作をこすという報告があります。難しいのは、尿酸値が高いほど痛風発作の確率が高いのは事実ですが、尿酸値が持続的に10mg/dLを超えていても発作を起こさない例もあり、「自分は大丈夫だから放っておく」とおっしゃる患者さんが少なくないことです。また、いったん関節内に溜まった尿酸結晶は数値に反映されないため尿酸値が正常でも痛風発作を起こすことがあり油断なりません。糖質の過剰摂取が痛風発作の頻度を上昇させるとの研究報告もあります。逆に、コーヒーや乳製品は痛風発作の頻度を下げるとの報告があります。
痛風の治療 〜受診してください
痛風発作の主体は関節内の炎症であり、血中の尿酸値が高いことではないので、治療の目的は尿酸の値を下げることではなく炎症を鎮めることです。患部は冷やすこと。マッサージやストレッチは症状を悪化させる可能性があります。運動やアルコールは発作がある間は厳禁です。
 薬としては消炎鎮痛効果があるものを選択しますが、市販の鎮痛薬に含まれるサリチル酸(アスピリン)は尿酸値を上昇させる働きがあるので使用しません。アスピリンを除く消炎鎮痛薬をつかいますが、効果がなければステロイド剤も使用します。発作初期に前兆があるような場合にはコルヒチンという薬を使うと発作が軽くすむ場合があります。
薬としては消炎鎮痛効果があるものを選択しますが、市販の鎮痛薬に含まれるサリチル酸(アスピリン)は尿酸値を上昇させる働きがあるので使用しません。アスピリンを除く消炎鎮痛薬をつかいますが、効果がなければステロイド剤も使用します。発作初期に前兆があるような場合にはコルヒチンという薬を使うと発作が軽くすむ場合があります。
いずれにせよ、適切な薬剤を短期間に十分量使う必要があり、基礎疾患による副作用の懸念や定期内服薬との関係もあるので、医療機関を受診して診断・治療をうけていただきたいと思います。

高尿酸血症 〜もはや国民病では?
血清の尿酸値が高い状態を「高尿酸血症」といいます。尿酸と痛風は密接に関係していますが、疼痛発作と血液検査異常に対して別の名称があたえられているのは別の疾患概念として扱われているということでもあります。
全人口で男性の20%、女性の5%が高尿酸血症(尿酸値 7.0mg/dL以上)との報告があり、潜在的な患者さんがいることを考えると、高尿酸血症は国民病と言って差し支えないレベルだと思います。

先ほど、「発作を起こしていないから尿酸値は高くても大丈夫」という意見を紹介しました。高尿酸血症は痛風の原因であるとともに、動脈硬化性疾患のリスク因子でもあります。尿酸結晶が血管の細胞を傷害することが知られており、糖尿病や高血圧と同様に管理する必要があるとされています。また、腎機能低下への影響もあるとされ、慢性腎臓病患者では無症状でも血清尿酸値が 8.0 mg/ dL を超えないように管理することがガイドラインにおいて提言されています。


高尿酸血症の治療 〜生活習慣病として
・食事療法
尿酸はプリン体が多く含まれる食材を取ることで上昇することが知られているので、痛風がなく軽度の尿酸値上昇例では食事療法から始めるます。
プリン体は肉類のレバーに多く含まれます。魚介類でも白子や内蔵を食べるマイワシ、カツオ、特に干物には多くプリン体が含まれます。また、糖質の過剰が尿酸値の上昇をもたらす報告、逆にビタミンCは尿酸値の上昇を抑制するとの報告があります。
プリン体というとビールが有名ですが、実際にはそれほど多く含まれません。しかし、アルコールは尿酸の排泄能力を低下させることがわかっているので、ビールにかかわらず飲酒は高尿酸血症には悪影響です。「ビールは飲まない、焼酎にしているから大丈夫」は高尿酸血症や痛風の診療では通らない、ということになります。

・運動療法
痛風発作の最中には強度の高い運動(無酸素運動)はご法度です。一方、高尿酸血症には適度な有酸素運動が重要で、尿酸上昇に関わるストレスの軽減や肥満の解消につながるため有意義です。ウォーキングや軽いジョギング、サイクリングなどに取り組んでください。
・薬物療法
血清尿酸の7〜8割は自分の体内でプリン体から生成しています。尿酸の体内での生成亢進と腎臓からの排泄低下(どちらかか両方か)が高尿酸血症の2つの大きな要因であり、薬物療法が検討される場合には尿酸生成を阻害する薬剤、もしくは尿酸排泄を促進する薬剤を選択します。痛風発作を起こしたことがある、生活習慣病の合併がある、尿酸値が9mg/dLを超える等の場合に薬の使用を検討します。
尿酸排泄促進薬:ベンズブロマロン、プロベネシド、ドヌラチド
尿酸生成阻害薬:アロプリノール、フェブキソスタット、トピロキソスタット
*腎機能や尿路結石、併用薬などを考慮して薬剤選択
「痛風と尿酸」をテーマにご紹介しました。痛風発作にしても高尿酸血症にしても、患者さんの背景(内服薬や併存疾患)により診療の方針は異なるので、かかりつけ医に相談していただくのがよいと思います。
まとめ
・ 「痛風」と「高尿酸血症」は密接に関係しているが、別の疾患概念である
・ 痛風発作は鎮痛薬を用いるが、市販薬には尿酸を上昇させるものがある
・ 高尿酸血症は動脈硬化のリスク因子であり、罹患率からは国民病と言ってもよい
・ 高尿酸血症では食事や運動といった生活習慣の是正が第一ではあるが、尿酸値が非常に高かったり、痛風や他の生活習慣病があるケースでは薬が必要となることが多い
・ 治療の方針や注意事項は患者さんごとに異なるので、かかりつけを受診すること