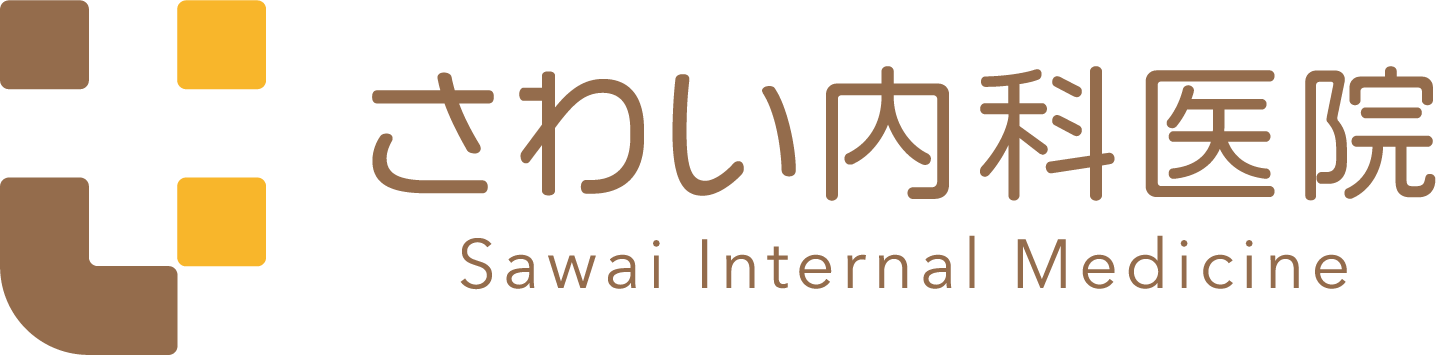お知らせNEWS
2024.04.26 「生活習慣病」について
生活習慣病とは?
〜「成人病」から「生活習慣病」へ、そしてこれからのつき合い方〜
「生活習慣病」という言葉、誰もが一度は耳にしたことがあると思います。字を見ればなんとなく意味はわかりますが、実はこの言葉、意外と奥が深いのです。

昔は「成人病」と呼ばれていました
高血圧や糖尿病、脂質異常症などは、今でこそ「生活習慣病」と呼ばれていますが、少し前までは「成人病」という名前で知られていました。
昭和30年代以降、日本では結核をはじめとする感染症の死亡率が大きく下がる一方で、がん、脳卒中、心臓病といった慢性疾患が新たな死因の上位を占めるようになっていきました。
年代ごとの主な死亡原因
| 年度 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
|---|---|---|---|---|
| 1935年 | 結核 | 肺炎・気管支炎 | 胃腸炎 | 老衰 |
| 1950年 | 結核 | 脳血管疾患 | 肺炎・気管支炎 | がん |
| 1960年 | 脳血管疾患 | がん | 心臓病 | 肺炎・気管支炎 |
当時は、こうした病気につながる高血圧、糖尿病、脂質異常症などは、主に「成人」に多く見られるため「成人病」と呼ばれていたわけです。
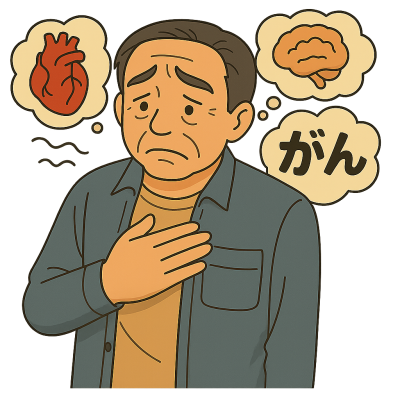
「生活習慣病」という考え方の登場
しかしその後の研究により、これらの病気は年齢だけでなく、普段の生活スタイル――たとえば食事や運動、タバコやお酒などの習慣――が大きく関係していることがわかってきました。
そこで、「加齢」ではなく「生活習慣」に着目して、これらの病気を見直す動きが出てきたのです。こうして生まれたのが「生活習慣病」という言葉です。
厚生労働省では、生活習慣病を「食事・運動・休養・喫煙・飲酒などの習慣が、発症や進行に深く関わる病気」と定義しています。
生活習慣との関係が深い主な病気
| 習慣 | 主な関連疾患 |
|---|---|
| 食習慣 | 糖尿病、肥満、高脂血症、痛風、大腸がん、歯周病など |
| 運動不足 | 糖尿病、肥満、高血圧、高脂血症など |
| 喫煙 | 肺がん、慢性気管支炎、COPD(肺気腫)、歯周病、心臓病など |
| 飲酒 | アルコール性肝障害など |

慢性疾患としての生活習慣病
〜「生活の中にある病気」と向き合うむずかしさ〜
生活習慣病は「慢性疾患」のひとつです。言葉は難しそうですが、急に症状が出る「急性疾患」との違いを見ればイメージしやすくなります。
| 特徴 | 急性疾患 | 慢性疾患 |
|---|---|---|
| 始まり | 急に | じわじわと進行 |
| 原因 | 明確なことが多い | 原因が複雑で多い |
| 期間 | 短期間で完結 | 長期間つづく |
| 検査・診断 | 明確な結果が出る | あいまいなこともある |
| 治る? | 治る可能性が高い | 完全に治ることは少ない |
生活習慣病の厄介な点は、日々の生活と切っても切り離せないこと。食べ物や運動、ストレスやタバコ・お酒といった生活習慣そのものを、ずっと、根本から変えていく必要があります。
そのため、患者さんから「一度始めた薬は、もう一生やめられないんでしょ?」とよく聞かれます。それも無理はありません。生活習慣の改善が難しい場合、薬に頼らざるを得なくなることが多いからです。
ただし、きちんと取り組めば薬を減らしたり、やめられたりするケースも実際にあります。だからこそ、最初からあきらめず、自分の生活と少しずつ向き合うことが大切です。
かかりつけ医として思うこと
〜「治す」よりも「うまくつき合う」ために〜
生活習慣病において、医師の役割は「治すこと」よりも、「合併症を防ぎながら、できるだけ普段どおりの生活を続けられるようにすること」だと考えています。
たしかに食習慣や運動、タバコやお酒といった要素は、病気の原因にもなります。でもそれらは同時に、患者さん自身の「暮らしそのもの」でもあります。「薬はできれば飲みたくない」「増やしたくない」と思うのも自然な気持ちでしょう。
だからこそ、医師としては、患者さんの考え方やライフスタイルに寄り添いながら、「どう病気とつき合っていくか」を一緒に考えていきたいと思っています。
病気に振り回されない日常を送るために。
そして、患者さん自身が「自分の暮らし方を自分で選んでいる」と思えるように。
そのお手伝いをするのが、私たちかかりつけ医の役割だと考えています。